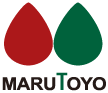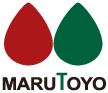ほうれん草の種まきの時期はいつ?「秋まき」を成功させる5つのステップをご紹介!
-

marutoyo U字溝鍬
2,508円
商品詳細を見る -

トンボ 超軽量 アルミ柄ショベル ラクワン丸 1.28kg
4,400円
商品詳細を見る -

ステンレス 三つ目鍬 ラセン木柄
7,678円
商品詳細を見る
「甘くて美味しいほうれん草を収穫するには、種まき時期はいつ頃がいいんだろう…」と迷われている方もおられるのではないでしょうか。ほうれん草栽培で最も重要なのは「秋まき(9月〜10月)」を選ぶ点にあります。
なぜなら、ほうれん草は寒さに当たると、凍結を防ぐために葉に糖分を蓄える性質があるからです。 本記事では、甘いほうれん草を育てるための秋まきの時期と、成功に導くステップ、春まき・夏まきの注意点まで詳しく解説します。

甘いほうれん草を収穫するなら「秋まき」が最適な理由

甘いほうれん草を収穫するなら「秋まき」といわれていますが、2つの理由があります。それぞれ詳しくみていきましょう。
理由①寒さに当たると甘みと旨みが増すため
家庭菜園でほうれん草を育てる際、最もおすすめの種まき時期は「秋(9月下旬〜10月下旬)」です。ほうれん草は冷涼な気候を好み、寒さに非常に強い野菜だからです。
秋に種をまくと、苗が大きく育つ時期と冬の寒さが訪れるタイミングが一致します。ほうれん草は、生育途中で寒さ(特に霜)に当たると、葉が凍らないように細胞内の水分濃度を高めようとします。
この過程でデンプンが糖に変わり、葉に糖分が蓄積されます。実際に、寒さにさらす「寒じめ栽培」という技術は、ほうれん草の糖度やビタミンC含有量を高める効果があると知られています。
農研機構の研究では、低温にさらすと、糖含量が顕著に増加するといわれています。
理由②害虫や病気が少なく管理しやすいため
ほうれん草栽培で悩ましいのが害虫や病気ですが、秋まきはこれらのリスクが大幅に減少します。気温が下がる時期は、アブラムシなどの害虫の活動が鈍くなり、被害を受けにくくなるためです。
また、高温多湿で発生しやすい「べと病」などの病気も、空気が乾燥し涼しくなる秋から冬にかけては発生が抑えられます。農薬に頼る頻度も減らせるため、初心者の方でも安心して管理できる点がメリットです。
甘いほうれん草を収穫するために、秋まきで成功する5つのステップ

秋まきで甘いほうれん草を確実に収穫するためには、いくつかの重要なステップがあります。特に土壌の酸度調整と間引きが成功の鍵を握ります。
ステップ①栽培に適した土を準備する
ほうれん草は酸性の土壌を極端に嫌います。日本の土壌は酸性に傾きやすい傾向があります。そのため、種まきの2週間ほど前に「苦土石灰(くどせっかい)」をまいてください。
これにより、土壌のpH(酸度)を中和(アルカリ性に近づける)ように調整します。 プランターで育てる場合は、市販の「野菜用培養土」を使うと簡単です。
培養土にはあらかじめ苦土石灰や肥料が配合されているため、土づくりの手間を省けます。
なお、家庭菜園用の土作りの方法については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
関連記事:【完全版】家庭菜園用の土作りは7ステップ|野菜がよく育つ土質の条件もご紹介! – マルトヨコーポレーション
ステップ②酸度調整後に種をまく
土壌の準備ができたら、いよいよ種まきです。種は「すじまき」と呼ばれる方法でまくのが一般的です。
深さ1cmほどのまき溝をまっすぐに作り、1〜2cm間隔で種をまいていきます。 ほうれん草の種は皮が硬く、発芽しにくい場合があります。一晩水につけてからまくと、発芽率が向上するのでおすすめです。
種をまいたら土を薄くかぶせ、手のひらで軽く押さえて土と種を密着させます。
ステップ③発芽まで水やりを欠かさない
種まき後から発芽するまでの約1週間〜10日間は、土の表面が乾かないように注意深く水やりを続けます。この時期に水切れを起こすと、発芽率が著しく低下してしまいます。 ただし、水のやりすぎは種の腐敗や病気の原因にもなります。
土の表面が乾いてきたら、ジョウロで優しくたっぷりと水を与えてください。
ステップ④元気な株を残すために間引きを行う
発芽して本葉(ギザギザしたほうれん草らしい葉)が1〜2枚出てきたら、最初の「間引き(まびき)」を行います。株同士が密集していると、光や栄養の奪い合いが起こり、大きく育ちません。
生育が悪いものや、葉の形が良くないものを中心に引き抜きます。そして、株間が3〜4cm程度になるように調整してください。
間引きは本葉が4〜5枚になった頃にもう一度行い、最終的に株間が5〜10cm程度にします。間引いた葉も、ベビーリーフとして美味しく食べられます。
ステップ⑤葉の色を見ながら追肥を行う
ほうれん草は生育期間が短いため、効率よく栄養を吸収させなければなりません。 株元にパラパラと化成肥料をまき、土と軽く混ぜ合わせます。
追肥の量が多すぎると、葉が苦くなる原因にもなります。肥料のパッケージに記載されている適量を守ってください。葉の色が薄くなってきたら、肥料切れのサインです。
ほうれん草の種まき時期は秋だけ?春まき・夏まきの3つの注意点

ほうれん草は秋まきが最適ですが、品種を選べば春や夏(高冷地)にまくのも可能です。しかし、秋まきとは異なる管理が必要になるため、以下の3つの点に注意してください。
注意点①春まき(3月~5月)は「とう立ち」のリスクがある
とう立ちとは、気温が上がり、日照時間が長くなる(長日条件)と、株が花芽をつけて茎を伸ばし始める現象を指します。 とう立ちが始まると、葉が硬くなり、食味が著しく低下してしまいます。
ほうれん草は、生物学的に長日植物に分類されます。1日の日照時間が一定以上(約12〜14時間)になると、花芽を形成する性質を持っています。春に栽培する場合は、とう立ちしにくい「晩抽性(ばんちゅうせい)」と呼ばれる品種を選ばなければなりません。
注意点②夏まき(7月~8月)は高温と病害虫対策が必要となる
夏まき(7月〜8月)は、主に冷涼な地域で行われますが、平地では高温による生育不良や病害虫のリスクが高まります。ほうれん草の生育適温は15〜20℃です。30℃近い高温が続くと発芽率が下がり、生育も停滞します。
また、高温多湿の環境では「べと病」などの病気が発生しやすくなるでしょう。夏まきに挑戦する場合は、耐暑性・耐病性のある品種を選び、遮光ネットで日差しを和らげたり、風通しを良くしたりする工夫が求められます。
注意点③栽培時期に適した品種を選ぶ
ほうれん草には、栽培時期によって適した品種があります。秋まきには寒さに強く甘みが出やすい品種を選びます。
春まきにはとう立ちしにくい晩抽性の品種、夏まきには暑さに強い品種を選ぶのが成功の第一歩です。 種のパッケージには、必ず「まき時期」や「品種の特性(例:晩抽性、耐病性)」が記載されています。
自分の栽培したい時期に合った種を選ぶようにしてください。
農具・園芸用品の購入に「マルトヨコーポレーション」がおすすめな理由

ほうれん草の栽培を始めるにあたり、プランターや土、肥料、ジョウロなどの道具を揃えなければなりません。信頼できる園芸用品を選ぶなら「マルトヨコーポレーション株式会社」がおすすめです。
マルトヨコーポレーションは、農具・園芸の総合商社として、初心者向けのスターターキットからプロが使用する専門的な資材まで、2,000点以上の豊富な商品を取り扱っています。3,980円以上の購入で送料無料のサービスや、栽培シーズンに合わせた商品の提案も魅力です。
「お値段以上に価値のある商品」を通じて、園芸初心者からベテラン農家まで幅広くサポートします。ほうれん草栽培に必要な道具一式を揃える際に、ぜひチェックしてみてください。⇒マルトヨコーポレーションの販売サイトはこちら
ほうれん草の種まき時期でよくある3つの質問

ほうれん草の種まき時期でよくある質問を解説します。それぞれ詳しくみていきましょう。
質問①ほうれん草の種がうまく発芽しない原因は何ですか?
発芽しない原因は「水切れ」と「土壌の酸度」の場合が多いです。ほうれん草の種は皮が硬いため、発芽まで土が湿った状態を保たなければなりません。
また、土壌が酸性のままだと、発芽してもすぐに枯れてしまう「立ち枯れ病」のような症状が出やすくなります。 種を一晩水につける、種まき前に苦土石灰で酸度調整を徹底するなどの対策が有効です。
質問②プランターでもほうれん草は育てられますか?
はい、育てられます。深さが15cm以上ある標準的なプランター(60cm幅など)を選んでください。 プランター栽培の場合、土が乾燥しやすいため、水やりは畑よりもこまめに行わなければなりません。
また、肥料分も流れやすいため、追肥を忘れずに行うのが美味しく育てるコツです。
なお、ほうれん草の他にもプランター栽培におすすめの野菜を知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
関連記事:【家庭菜園】プランター栽培におすすめの野菜15選|プランター栽培の手順も詳しくご紹介!
質問③ほうれん草に連作障害はありますか?
ほうれん草には「連作障害(れんさくしょうがい)」があります。同じ場所(土)で連続してほうれん草を栽培すると、土壌中の特定の栄養素が不足したり、土壌伝染性の病原菌が増えたりして、生育が悪くなる現象です。
畑で栽培する場合は、一度ほうれん草を育てた場所では、最低でも1〜2年はほうれん草(アカザ科の野菜)の栽培を避けてください。プランターの場合は、新しい培養土を使えば問題ありません。
なお、連作障害の予防と改善に役立つ対策方法については、こちらの記事でご紹介しています。
関連記事:連作障害の予防と改善に役立つ対策方法は4つ|原因やよくある質問もご紹介! – マルトヨコーポレーション
甘くて美味しいほうれん草を収穫するために、最適な時期に種をまこう!

ほうれん草の種まき時期は、美味しいほうれん草を収穫したいなら「秋まき」が最適です。寒さに当てると甘みが引き出されます。
家庭菜園ならではの格別な味わいを楽しめます。 成功のためには、以下の5つのステップを丁寧に行うことが大切です。
-
ステップ①栽培に適した土を準備する
-
ステップ②酸度調整後に種をまく
-
ステップ③発芽まで水やりを欠かさない
-
ステップ④元気な株を残すために間引きする
-
ステップ⑤葉の色を見ながら追肥を行う
「土壌の酸度調整」は、ほうれん草栽培において最も重要なポイントの一つです。苦土石灰や市販の培養土をうまく活用してください。
春まきや夏まきには、とう立ちや高温といったリスクが伴いますが、時期に適した品種を選べば栽培は可能です。本記事を参考に、ぜひご自身の環境に合った種まき時期を選び、美味しいほうれん草の収穫に挑戦してみてください。
なお、マルトヨコーポレーション株式会社は、農具・園芸の専門商社です。家庭菜園やガーデニングに初めて挑戦する方におすすめの手軽な園芸用品を扱っています。さらに、農業を本格的に営むプロの方々が求める高品質な農具・資材まで、幅広く取り揃えています。
豊富な品揃えに加えて、使いやすさや耐久性にこだわった商品が充実しています。ぜひ一度、マルトヨコーポレーションの販売サイトをチェックしてみてください。⇒マルトヨコーポレーションの販売サイトはこちら

-

marutoyo U字溝鍬
2,508円
商品詳細を見る -

トンボ 超軽量 アルミ柄ショベル ラクワン丸 1.28kg
4,400円
商品詳細を見る -

ステンレス 三つ目鍬 ラセン木柄
7,678円
商品詳細を見る