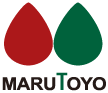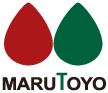庭の落ち葉を有効活用!堆肥の作り方と失敗しない5つの注意点をご紹介!
-

土のう袋 48cm×62cm 10枚入り ホワイト
450円
商品詳細を見る -

marutoyo スチールレーキ 14本爪
2,178円
商品詳細を見る -

marutoyo 木柄ショベル 1.6kg
1,848円
商品詳細を見る
庭や道路を彩る落ち葉は、秋の風物詩ですが、いざ掃除となると大量の落ち葉の処分に頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。実は、その落ち葉は捨てずに、植物が元気に育つための栄養豊富な「堆肥」として再利用できるのをご存知でしたか?
落ち葉堆肥は、ゴミを減らせるだけでなく、土壌を豊かにしてくれる、まさに一石二鳥の土壌改良材です。本記事では、落ち葉堆肥の基本的な作り方から、初心者でも失敗しないための5つのコツまで、詳しく解説します。
本記事を読めば、自宅の落ち葉を有効活用し、家庭菜園やガーデニングに役立つ堆肥を自作できるようになるでしょう。

落ち葉で堆肥を作る3つのメリット

落ち葉堆肥は、作る手間や時間はかかるものの、それを補ってあまりある多くのメリットがあります。ここでは、落ち葉を堆肥化する場合の具体的なメリットを3つご紹介します。
1.ゴミの削減と肥料費の節約
自宅の庭や公園などで集めた落ち葉は、堆肥にすれば、ゴミとして処分する必要がなくなります。これにより、家庭から出るゴミの量を減らし、持続可能な暮らしにつながります。
また、土壌改良材として使う堆肥を自作できるため、ホームセンターなどで購入する肥料代を節約できるのも大きなメリットです。畑や家庭菜園の規模が大きいほど、その節約効果は高くなります。
2.土壌改良効果による植物の生育促進
落ち葉堆肥は、市販の化学肥料とは異なり、土壌の物理的な性質を改善する効果が高いことが特徴です。堆肥を土に混ぜれば、土の中に隙間ができて通気性や排水性が向上し、同時に保水性も高まります。
これにより、土がふかふかと柔らかくなり、植物の根が張りやすくなるため、健全な生育を促します。特に、水はけが悪い粘土質の土や、水持ちが悪い砂質の土に混ぜると、その効果を実感しやすくなるでしょう。
3.病害虫に強い健康な土づくり
落ち葉堆肥には、さまざまな微生物が豊富に含まれています。これらの微生物は、土の中で互いに助け合いながら、植物にとって良い環境を作ります。
土壌中の微生物が活発に活動すれば、植物の病害虫に対する抵抗力が高まり、より丈夫な作物が育つことが期待できます。また、市販の肥料に比べ、植物に必要なミネラル分や栄養素を自然な形で供給できるため、野菜の味や風味を向上するでしょう。
なお、古い土の再生方法について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
関連記事:古い土の再生方法は5ステップ|古い土がガーデニングに適さない理由を詳しく解説します!
落ち葉での堆肥の作り方と失敗しないための手順は5ステップ

落ち葉堆肥は、正しい手順とポイントを押さえれば、初心者でも簡単に作れます。ここでは、具体的な作り方と、失敗を防ぐための5つのコツを解説します。
ステップ1.広葉樹の落ち葉を集める
落ち葉堆肥に適しているのは、分解が早い広葉樹の落ち葉です。クヌギ、ナラ、ケヤキ、カシワなどの落ち葉は、微生物が分解しやすく、質の良い堆肥になります。
一方、マツやスギといった針葉樹、ツバキやイチョウなどの常緑樹は、分解に時間がかかるため、避けるのが無難です。落ち葉を集める際は、大きな枝や石、ゴミなどを取り除いておきましょう。
ステップ2.堆積場所を確保する
落ち葉を積み重ねるための場所を確保します。地面に穴を掘る方法や、ベニヤ板や木枠などで囲いを作る方法があります。場所は、風通しが良く、水はけが良い場所を選びましょう。水が溜まる場所だと、落ち葉が腐敗して悪臭の原因になるため注意が必要です。
また、ある程度の量がないと発酵が進みにくいため、最低でも40〜90cm程度の高さになるように積み重ねましょう。
ステップ3.水と米ぬかを加えて積み重ねる
確保した場所に、落ち葉を20cm程度の厚さに敷き、その上に土を薄く被せます。この作業を何度も繰り返して、ミルフィーユ状に積み重ねるのがコツです。
土には、発酵を促す微生物が多く含まれています。さらに、発酵を早めたい場合は、落ち葉の重量の1〜2%程度の米ぬかや油粕を混ぜるのが効果的です。
最後に、落ち葉全体がしっとりと湿るように水をたっぷりとまき、足で踏み固めて空気を抜きます。
ステップ4.定期的に「切り返し」を行う
堆肥づくりの成否を分けるのが「切り返し」という作業です。切り返しとは、積み重ねた落ち葉をスコップなどで混ぜる作業のことです。
これにより、空気や水分が全体に行き渡り、微生物が活発に活動して発酵が進みます。仕込みから1〜2ヶ月後から月に1回程度のペースで、堆肥全体の色が均一になるまで定期的に行いましょう。
ステップ5.完熟を見極める
落ち葉堆肥は、一般的に1年程度で完成します。完成した堆肥は、落ち葉の形がほとんどなくなり、サラサラとした黒っぽい土になっています。
土を握るとだんご状に固まり、嫌な臭いがしないのも完熟のサインです。発酵が不十分な未熟堆肥をそのまま土に混ぜると、土中の窒素が奪われてしまい、植物の生育不良につながる可能性があるため、必ず完熟した状態で確認してから使用しましょう。
落ち葉の堆肥を作る際の3つの注意点

落ち葉堆肥は、正しい手順で作成すれば環境に優しい優れた土壌改良材になりますが、作り方を間違えると、悪臭が発生したり、植物の生育を妨げたりする原因になります。ここでは、落ち葉堆肥を作る上で特に注意すべきポイントを解説します。
1.分解しにくい落ち葉は避ける
落ち葉堆肥に適しているのは、微生物が分解しやすい広葉樹の落ち葉です。クヌギやナラ、ケヤキなどがこれにあたります。
一方で、マツやスギといった針葉樹や、ツバキ、サザンカなどの常緑樹は、葉が硬く油分を多く含むため、分解に時間がかかります。これらを多く含めると、堆肥化がなかなか進まず、完成までに長期間を要するため注意が必要です。
2.水分量を適切に保つ
落ち葉堆肥の発酵には、適度な水分が不可欠です。水分が少なすぎると微生物の活動が鈍り、発酵が進みません。逆に水分が多すぎると、酸素が不足して腐敗が進み、嫌な臭いの原因となります。理想的な水分量は、落ち葉を握って水分がにじみ出るか出ないかぐらいです。
季節や天候によって乾燥したり湿りすぎたりする場合があるため、定期的に水分量をチェックし、調整しましょう。
3.未熟堆肥は使用しない
堆肥として完成する前の未熟堆肥は、絶対に土に混ぜないようにしましょう。未熟堆肥を土に混ぜると、土中の微生物が分解のために窒素を消費してしまい、植物が栄養不足になります。
その結果、葉が黄色くなったり、生育が悪くなったりといった生育障害を引き起こす可能性があります。完成した落ち葉堆肥は、見た目が黒っぽく、サラサラとした土状になっており、嫌な臭いもありません。
この状態を確認してから使用しましょう。
農具・園芸用品の購入に「マルトヨコーポレーション」がおすすめな理由

「マルトヨコーポレーション株式会社」は、農具・園芸の総合商社として、「簡単に始められる!」をコンセプトにした初心者向け商品から、プロ向けの専門的な商品まで、2,000点以上の幅広い商品を取り扱っています。
豊富な商品ラインナップに加え、昔ながらの道具にもこだわっているため、家庭菜園やガーデニングに初めて挑戦する方から、本格的な農作業を行うプロの方まで、幅広いニーズに対応できるのが強みです。
また、3,980円以上の購入で送料無料になるサービスや、栽培シーズンに合わせた商品提案もあり、必要な道具を無駄なく手に入れられる点も大きな魅力です。⇒マルトヨコーポレーションの販売サイトはこちら
落ち葉の堆肥の作り方でよくある3つの質問

落ち葉の堆肥の作り方でよくある質問をご紹介します。それぞれ詳しく解説します。
質問1.落ち葉堆肥はどんな植物に使うのがおすすめですか?
落ち葉堆肥は、土壌の通気性や保水性を高める効果が高いため、ほとんどの植物に有効です。特に、土が硬くなりがちな畑や花壇の土に混ぜ込むと、団粒構造が形成されて土がふかふかになり、野菜や花が育ちやすい環境になります。
また、鉢植えやプランターの土に混ぜると、水はけが良くなり、根腐れを防ぐ効果も期待できます。
質問2.落ち葉堆肥を作るのに適した時期はありますか?
落ち葉堆肥を作るのに最も適しているのは、落ち葉が大量に集まる秋から冬にかけての時期です。この時期に仕込みを始めると、春には微生物の活動が活発になるため発酵が順調に進み、翌年の秋頃には完熟堆肥として使用できる状態になります。
堆肥作りは時間がかかるため、夏野菜の植え付けや次のガーデニングシーズンに間に合わせたい場合は、必要な時期から逆算して、できるだけ早く作業を始めましょう。
質問3.落ち葉堆肥作りに必要な道具は何ですか?
落ち葉堆肥を作る際には、特別な機械は必要ありませんが、効率良く作業するための道具をいくつか準備しておくと便利です。まず、落ち葉を集めるための熊手やレーキ、堆積場所へ運ぶための一輪車や土嚢袋があると、大量の落ち葉もスムーズに扱えます。
また、切り返し作業には、スコップやクワが役立ちます。さらに、発酵を促す米ぬかや、雨風から堆肥を守るブルーシートなどもあると、より質の高い堆肥を効率的に作れるでしょう。
これらの道具は、ホームセンターなどで手軽に揃えることが可能です。
なお、岡山でおすすめの園芸用品店については、こちらの記事でご紹介しています。
関連記事:岡山でおすすめの園芸用品店7選|選び方のポイントやよくある質問まで詳しく解説します! – マルトヨコーポレーション
まとめ

落ち葉堆肥は、庭や公園で集めた落ち葉を再利用して、ゴミを減らし、植物が元気に育つための質の良い土を作れる、環境にも家計にも優しい方法です。本記事でご紹介したように、落ち葉堆肥作りは、広葉樹の葉を集め、土や米ぬかと一緒に積み重ね、定期的に切り返しを行うといったシンプルな手順で進められます。
ただし、完熟していない未熟堆肥をそのまま使ってしまうと、かえって植物の生育を妨げてしまう可能性があるため、完成の見極めが非常に重要です。落ち葉が大量に出る季節に、本記事を参考に、落ち葉堆肥づくりに挑戦してみてはいかがでしょうか。
愛情を込めて作った堆肥で、家庭菜園やガーデニングをより一層楽しんでください。
なお、マルトヨコーポレーション株式会社は、家庭菜園やガーデニングに初めて挑戦する方におすすめの手軽な園芸用品から、農業を本格的に営むプロの方々が求める高品質な農具・資材まで、幅広く取り揃えている農具・園芸の専門商社です。
豊富な品揃えに加えて、使いやすさや耐久性にこだわった商品が充実しており「庭づくりや農作業をもっと楽しく、もっと快適にしたい」という幅広いニーズにお応えしています。ぜひ一度、マルトヨコーポレーションの販売サイトをチェックしてみてください。⇒マルトヨコーポレーションの販売サイトはこちら

-

土のう袋 48cm×62cm 10枚入り ホワイト
450円
商品詳細を見る -

marutoyo スチールレーキ 14本爪
2,178円
商品詳細を見る -

marutoyo 木柄ショベル 1.6kg
1,848円
商品詳細を見る