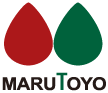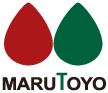籾殻堆肥のメリット・デメリットとは?特徴や作り方、よくある質問まで詳しくご紹介します!
-

岡山県産 もみがら 約20L
498円
商品詳細を見る -

日本マタイ 防草シート用固定釘 50P
3,080円
商品詳細を見る -

鳩よけネット 25mm菱目 2m×8m グレー
2,420円
商品詳細を見る
籾殻堆肥は、籾殻を家畜糞や米ぬかなどと一緒に発酵させて作られる資材です。化学肥料の削減や循環型農業の推進に役立ち、コスト削減や環境保護にも貢献できる資材として注目されています。
本記事では、籾殻堆肥のメリット・デメリットや特徴、作り方をご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

籾殻堆肥とは?

籾殻堆肥は、籾殻を家畜糞や米ぬかなどと一緒に発酵させて作られる資材で、主に土壌改良に使われます。堆肥化すると、籾殻は腐熟して、土壌の物理性や生物性を改善するのが特徴です。
土をやわらかくして、土壌微生物を増やして健康な土を作る手助けをします。また、家畜糞を使った堆肥は、カリ成分が高く、肥料としても効果的です。化学肥料の削減や循環型農業の推進に役立ち、コスト削減や環境保護にも貢献できる資材です。
籾殻堆肥の特徴
籾殻は肥料成分が少ないため、施肥過剰による肥料焼けのリスクを軽減して、根のダメージを最小限に抑えられます。また、土壌の通気性を改善して、根腐れの発生を抑制するのに効果的です。
籾殻を土壌に混ぜると、水分の保持力や排水性が向上して、作物の成長環境が整えられます。微生物による有機物分解には時間がかかりますが、長期的に土壌の質を高め、作物の育成をサポートする素材となります。
籾殻堆肥のメリットは3つ

次は、籾殻堆肥のメリットについて解説します。
- マルチング資材として利用できる
- 土壌改良材として利用できる
- 畜舎敷料資材として利用できる
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.マルチング資材として利用できる
畑の表面に直接敷くマルチングにより、雑草の発芽を抑制して、病害虫の被害を軽減する効果が期待できます。さらに、土壌の水分蒸発を抑え、冬には乾燥から土を守り、夏には高温から作物の根を保護します。
雨による土壌の固結を防ぎ、土壌の保温・保湿効果も発揮されるため、栽培環境を整えるために効果的な方法です。このため、土作りに簡便に活用できる素材として注目されています。
2.土壌改良材として利用できる
籾殻は、微生物の活動を促進して、土壌の団粒構造を形成する効果があります。分解には時間がかかりますが、微生物が少しずつ籾殻を分解すれば、土壌がふっくらとした構造に変わっていきます。
また、土壌の通気性や排水性を向上させ、固まった土を改善するのに効果的です。注意点として、籾殻を大量に混ぜると、土壌の保水性が一時的に低下する場合がありますが、時間が経つと馴染んで元の状態に戻ります。
3.畜舎敷料資材として利用できる
畜舎では、家畜の快適さを保ち、糞尿処理を効率化するために、わらや籾殻、牧草などが敷料として利用されます。昔から稲や麦のわらが一般的に使われていましたが、近年ではおが粉やバークといった木材系の素材に加え、籾殻やキノコ菌床なども用いられる場合が多いです。
籾殻は、粉砕してから使う場合もあり、形状や状態に応じて敷料としての使い勝手が変わります。これらの素材は、畜舎の清潔さを保つ役割も果たしています。
籾殻堆肥のデメリット

籾殻堆肥のデメリットは、以下のとおりです。
- 保水性の低下
殻を大量に混ぜると、土壌の保水性が低下して、乾燥しやすくなる
- 窒素飢餓のリスク
炭素率が高い籾殻は、微生物が窒素を消費するため、窒素飢餓を覚悟して、作品の生育が阻害される可能性がある
- 発酵に時間がかかる
籾殻を堆肥化するには、米ぬかや鶏糞などを混ぜて微生物で発酵させる必要があり、時間と手間がかかる
籾殻堆肥の作り方

籾殻堆肥の作り方は、以下のとおりです。
- 籾殻、米ぬか、鶏糞などを層状に積み重ねる。もみ殻と混ぜると微生物の活動が活発化して、堆肥化が進む
- 適量の水を加えてしっかり踏み固め、全体をブルーシートで覆う
- 発酵が始まると内部温度が上昇する。最初の1か月間は週に1回の切り返しが必要
- 月に1回程度切り返しを行う
- 数か月後には黒っぽくなり、アンモニア臭が消えると完成
籾殻堆肥 デメリットでよくある3つの質問

最後に、籾殻堆肥 デメリットでよくある質問について紹介します。
- 質問1.土壌改良材として使用する場合の注意点は?
- 質問2.籾殻堆肥の入手方法は?
- 質問3.肥料と堆肥の違いとは?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.土壌改良材として使用する場合の注意点は?
籾殻は土壌改良に役立つものの、過剰に使用すると「窒素飢餓」を引き起こすリスクがあります。これは、土壌微生物が炭素(C)と窒素(N)を取り込んで活動する際、炭素が多すぎると微生物が窒素を優先的に利用して、作物に必要な窒素が不足するためです。
さらに、C/N比が20を超えると、窒素不足が生じやすくなります。このため、適切なバランスを保ちながら使用することが大切です。
質問2.籾殻堆肥の入手方法は?
籾殻堆肥は、籾殻を集めて環境菌や米ぬかを加え、発酵させて作られます。この材料は、ライスセンターや稲作農家、コイン精米所、農産物直売所などで手軽に入手可能です。
また、ホームセンターやオンライン通販でも購入できるため、堆肥作りに必要な資材を揃えるのは比較的簡単です。籾殻堆肥は手軽に作れるうえに、土壌改良にも役立つため、家庭菜園や農業で広く活用されています。
なお、岡山でおすすめの園芸用品店については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:岡山でおすすめの園芸用品店7選|選び方のポイントやよくある質問まで詳しく解説します!
質問3.肥料と堆肥の違いとは?
肥料は、作物の成長を促進するために使用され、堆肥は土壌の改良を目的としています。どちらも「豊かな作物を育てる」ためには欠かせない資材です。
堆肥で土をふっくらとさせて、肥料で作物に必要な栄養を補うと、おいしい野菜を育てられます。市場には多くの肥料や堆肥があり、畑や作物に合ったものを選ぶことが成功のポイントになります。
まとめ

本記事では、籾殻堆肥のメリット・デメリットや特徴、作り方をご紹介しました。
籾殻堆肥は、肥料成分が少ないため、施肥過剰による肥料焼けのリスクを軽減して、根のダメージを最小限に抑えられます。また、土壌の通気性を改善して、根腐れの発生を抑制するのに効果的です。
籾殻を土壌に混ぜると、水分の保持力や排水性が向上して、作物の成長環境が整えられます。このため、マルチング資材や土壌改良剤、畜舎敷料資材として利用ができます。
しかし、殻を大量に混ぜると保水性の低下や、炭素率が高い籾殻を混ぜると窒素飢餓のリスクがあり、発酵に時間がかかる点はデメリットです。
また、籾殻堆肥は、籾殻や米ぬか、鶏糞などを層状に積み重ねて、もみ殻と混ぜると微生物が活発化して、堆肥化が進みます。しかし、定期的な切り返しをする必要があるため、注意しましょう。
なお、マルトヨコーポレーション株式会社は、農具・園芸の総合商社として、初心者用商品からプロの方にご満足いただける商品まで、幅広い商品を取り扱っています。⇒マルトヨコーポレーション株式会社

-

岡山県産 もみがら 約20L
498円
商品詳細を見る -

日本マタイ 防草シート用固定釘 50P
3,080円
商品詳細を見る -

鳩よけネット 25mm菱目 2m×8m グレー
2,420円
商品詳細を見る