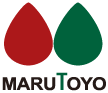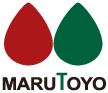ブルーシートの規格の見方!失敗しない選び方と耐久性の違いを解説
建設現場、家庭の日曜大工まで、私たちの生活に欠かせないブルーシート。しかし「#3000」「#4000」といった規格表示の意味を正確に理解している方は意外と少ないのではないでしょうか?
本記事では、JIS規格に基づいたブルーシートの正しい選び方から、番手別の特徴、用途に応じた最適な選択方法まで徹底解説します。あなたのニーズに最適な一枚を見つけるためにお読みください。

ブルーシートとは?基本知識と用途

ブルーシートは、青色にコーティングされたポリエチレン製の糸を織って作られた軽量で耐久性・防水性に優れた多目的シートです。家庭では洗車時の水はね防止、レジャーシート、庭の草刈りの集草、ガレージの雨よけなどに活用され、災害時や工事では被災家屋の屋根養生、資材保護、仮設テントの屋根材、土砂崩れ防止シートとしても重宝します。
塩化ビニル製のビニールシートと比較して強度が高く屋外使用に適しています。さらに、ハサミやカッターで簡単に切断・加工でき、キャンプや野外イベントの地面保護・荷物覆いにも利用可能です。厚みは約0.1~0.5mmが一般的で、用途に応じて選べます。
ブルーシートの規格表示

参考:JIS規格
ブルーシートを購入する際には、製品に表示されている規格表示を正しく理解しましょう。規格表示には主にJIS規格、番手表示、サイズ表記の3つの要素があります。
JIS規格とは日本工業規格のことで、ブルーシートの品質や性能を保証する基準となっています。JIS規格に適合した製品は耐久性や安全性が一定水準以上です。
番手表示は「#(シャープ)」の後に数字が続く形で表示され、シートの重量(厚さ)を示します。
|
番手表示 |
意味 |
|
#3000 |
3.6m×5.4mサイズで約3kgの重さ |
|
#2000 |
3.6m×5.4mサイズで約2kgの重さ |
|
#1000 |
3.6m×5.4mサイズで約1kgの重さ |
サイズ表記は「3.6×5.4m」のように表示されますが、これは折り返し前の「呼び寸法」です。実際の仕上がりサイズは四辺を折り返してハトメ(穴)を取り付けるため、約10cm小さくなると覚えておきましょう。
耐久性で選ぶ番手別の特徴

ブルーシートは番手によって耐久性が大きく異なります。用途に合わせた適切な番手選びが重要です。
軽量タイプ(#1000〜#2000)の特徴と適した用途
軽量タイプのブルーシートは、薄手で軽量なため持ち運びや設置が容易で、折りたたみやすく収納スペースを取らないのが特長です。コストパフォーマンスも高く、番手#1000〜#1500は簡易的な目隠しやレジャーシート(1回限りの使用)、#1500〜#2000は屋内養生や数日〜数週間の短期防水カバーに最適です。
ただし長期屋外使用は紫外線劣化や強風による破損リスクが高いため、用途や使用環境に合わせた番手選びが重要です。生地が薄く透けやすいものもあるため、プライバシー保護が必要な場合は番手や色合いも考慮してください。
また、切断加工が容易で、DIYや仮設作業にも向いています。
中量タイプ(#3000)の特徴と適した用途
中量タイプの#3000ブルーシート(厚さ約0.26mm、重量は1㎡あたり約3kg)は、軽量タイプより強度が高く、かつ扱いやすさを両立しています。屋外で3~6ヶ月使用に耐え、一般的な雨風に対応します。
災害時の屋根応急処置、建設資材カバー、中期的な屋外イベントの雨よけ、農業用ハウス補修、土木工事の養生など幅広く活用でき、家庭備蓄にも最適です。長期使用時は定期点検を行い、劣化防止を心がけましょう。
また、ポリエチレン製のシートとして防水性・耐候性に優れ、軽量ながら撥水性を保持します。DIYや野外作業、家具保護などにも応用でき、汎用性が高いのも魅力です。
価格も比較的手頃なため、コスト重視の選択肢として第一に挙げられます。
重量タイプ(#4000以上)の特徴と適した用途
重量タイプの#4000以上のブルーシートは、厚み約0.36mm以上で引き裂き強度や耐候性・耐水性に優れ、紫外線劣化にも強い長期使用向けシートです。強風下での安定性が高く、金属製ハトメで固定できるため、災害時の長期屋根養生、建設現場の資材カバー、農業用ハウス補強、長期的な野外イベントの雨除け、倉庫の屋根・壁補修など過酷な環境下で活躍します。
価格はやや高めですが、耐久性を活かした長期使用で頻繁な交換コストを削減できるためコストパフォーマンスに優れます。農業や土木施工でも多用され、取り扱いには複数人と定期点検を推奨します。保管時は巻き取り乾燥させ風の影響を避けると劣化抑制につながります。
番手別の耐用年数の目安
ブルーシートの耐久性は番手によって大きく異なります。一般的な使用環境での番手別の耐用年数の目安は以下の通りです。
|
番手 |
耐用年数の目安 |
|
#1500 |
約1~3ヶ月 |
|
#2000 |
約3~6ヶ月 |
|
#2500 |
約7~9ヶ月 |
|
#3000 |
約9~12ヶ月(約1年) |
|
#4000 |
約2~3年 |
|
#5000 |
約4~5年 |
#1300以下の薄手タイプは1ヶ月程度で劣化が始まるため、一時的な使用や使い捨てに向いています。屋外で長期間使用する場合は、#3000以上のUV材添加タイプを選ぶのをおすすめします。
なお、これらの耐用年数は使用環境によって大きく変動するでしょう。直射日光や風雨にさらされる屋外では劣化が早まり、室内使用では長持ちします。
また、長寿命タイプやUV材添加タイプを選べば、通常より長期間の使用が可能になります。
目的別ブルーシートの選び方

具体的な使用シーンに応じた選び方のポイントを詳しく解説していきます。
屋外長期使用のために選ぶ
屋外で長期間ブルーシートを使用する場合は、耐候性と耐久性に優れた製品を選ぶのが重要です。長期使用に適したブルーシートの選び方のポイントは以下の通りです。
まず、番手は#3000以上を選びましょう。特に#4000や#5000などの高番手製品は厚みがあり、引裂強度・引張強度に優れているため、風や雨に強く長期使用に適しています。また、防水性能も重要です。
屋根の養生や資材の野積みなど、雨風にさらされる場所では、ハトメ(穴)の間隔が狭いものを選ぶと、しっかり固定できて風による破損を防げます。寒冷地で使用する場合は、低温でも硬化しにくい特殊加工されたブルーシートを選ぶと、冬場でも割れにくく長持ちします。
防水・防塵目的で選ぶ
防水性・防塵性を重視する際は、#3000以上の高番手ブルーシートを選びましょう。防水用途では耐水圧性能が高い#4000以上を選び、継ぎ目の少ない一枚物タイプ・ハトメ付きでしっかり固定すると長時間の雨でも浸水を防げます。
防塵用途では静電気で粉塵を吸着する特殊加工シートが最適。表面加工によりホコリの拡散を抑え、ウエスでの拭き取り清掃が容易です。長期屋外使用時は定期的な点検と紫外線劣化対策を忘れずに行い、防水・防塵効果を長持ちさせましょう。
番手によって厚みや重量が異なるため、持ち運びや設置のしやすさも考慮し、複数枚用意するのがおすすめです。乾燥後に保管し、カビや劣化を防ぎましょう。
軽量性と携帯性を選ぶ
アウトドアやイベントに持ち運びしやすいブルーシートを選ぶなら、番手#1000〜#2000の軽量タイプがおすすめです。特に1.8×1.8 mや2.7×3.6 mなど小ぶりなサイズを選ぶと荷物がかさばらず、折りたたんでコンパクトに収納できます。
必要最小限のサイズと軽さで雨よけや地面シートとして活躍し、使用後は丁寧に折りたたんでおくと次回もスムーズに広げられます。
コストパフォーマンスで選ぶ
ブルーシートは使用期間に応じて最適な番手が変わり、コストパフォーマンスを最大化できます。短期利用(1ヶ月未満)であれば番手#1000~#1500の軽量タイプがおすすめで、50m巻が1,500~2,500円程度です。
日曜大工や一時的な養生に十分耐えうる性能です。数ヶ月程度の中期利用では番手#2000~#3000を選ぶと、100m巻が5,000~7,000円で手に入り、耐久性と価格のバランスがよくなります。
実際、番手#1000の100m巻は3,000円程度で耐用期間2~3ヶ月、1ヶ月あたり約1,000円。一方、番手#3000なら6,000円ほどで約1年使え、月あたり500円程度の計算になります。長期的には初期投資が高くても耐用期間の長い高番手を選んだほうが、結果的に交換頻度やコストを抑えられます。
また、ハトメなしのロールタイプはハトメ付きより安価なので、自分で固定できる場合はより経済的です。用途や設置環境に合わせ、番手・ロール形式を上手に選びましょう。
農具・園芸用品の購入に「マルトヨコーポレーション」がおすすめな理由

「マルトヨコーポレーション株式会社」は、農具・園芸の総合商社として「簡単に始められる!」をコンセプトとした初心者用商品から、プロの方にご満足いただける商品まで、2,000点以上の幅広い商品を取り扱っています。
また、3,980円以上で送料無料のサービスや栽培シーズンに合わせた商品のお届けも可能です。さらに、昔ながらの道具にもこだわり続けており、園芸初心者や農家さんの味方として「お値段以上に価値のある商品」を提供しています。⇒マルトヨコーポレーションの販売サイトはこちら
ブルーシートの規格でよくある質問3つ

ブルーシートの規格に関する3つの質問と回答をまとめました。
質問1.「UV加工」と表示されたブルーシートは通常のものと何が違うのですか?
「UV加工」と表示されたブルーシートは、UV加工により紫外線による劣化を防ぐ効果があり、屋外での長期使用に適しています。通常のブルーシートより2〜3倍長く使用できる場合が多く、色あせや脆化が抑えられます。
UV加工を施すための追加コストがかかるため、通常品より高価格です。特に屋根の応急処置や長期の屋外保管など、太陽光に長時間さらされる用途に最適です。
質問2.輸入品ブルーシートとJIS規格品の違いは何ですか?
輸入品ブルーシートは価格が安い反面、製造国ごとに品質基準が異なるため耐久性や性能にばらつきがあります。一方、JIS規格品はJIS L 1902準拠で引張強度・防水性・耐候性を厳しく検査・保証しており、#3000番手で1〜2年の耐用年数が期待できます。
短期的な養生や軽作業には輸入品でも十分ですが、災害復旧や屋根の応急処置など重要用途には品質が安定したJIS規格品を選ぶのが安心です。購入時はパッケージのJISマークや製造元・製造国表示を必ず確認し、用途と使用期間に合わせて最適なシートを選びましょう。
質問3.JIS規格に準拠していないブルーシートを使っても問題ないのでしょうか?
JIS規格(日本工業規格)に準拠していないブルーシートでも、用途によっては問題なく使用できます。ただし、JIS規格品は引張強度や防水性など一定の品質基準を満たすことが保証されているため、特に長期使用や過酷な環境での使用を想定する場合は、JIS規格品を選びましょう。
非JIS規格品は価格が安い傾向がありますが、同じ番手表示でもJIS規格品より耐久性が劣る場合があるでしょう。短期間の軽い用途であれば、非JIS規格品でも十分対応できます。
まとめ

本記事では、JIS規格に基づいたブルーシートの番手表示(#1000~#4000以上)の意味と各タイプの耐久性を解説しました。ブルーシート選びでは、使用目的(長期使用・防水防塵・携帯性・コスト)に合わせた番手選びが重要です。
この情報を参考に、あなたの用途に最適なブルーシートを選んでください。
なお、マルトヨコーポレーション株式会社は、家庭菜園やガーデニングに初めて挑戦する方におすすめの手軽な園芸用品から、農業を本格的に営むプロの方々が求める高品質な農具・資材まで、幅広く取り揃えている農具・園芸の専門商社です。
豊富な品揃えに加えて、使いやすさや耐久性にこだわった商品が充実しており「庭づくりや農作業をもっと楽しく、もっと快適にしたい」という幅広いニーズにお応えしています。ぜひ一度、マルトヨコーポレーションの販売サイトをチェックしてみてください。⇒マルトヨコーポレーションの販売サイトはこちら